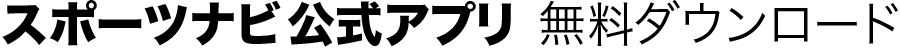横浜Mでユース昇格を逃した中村俊輔は桐光学園で大きく成長。選手権ではファンタスティックなプレーを随所で披露した【写真:青木紘二/アフロスポーツ】
横浜Mでユース昇格を逃した中村俊輔は桐光学園で大きく成長。選手権ではファンタスティックなプレーを随所で披露した【写真:青木紘二/アフロスポーツ】
4つのポジションの中で最も得票率に差がなく、大激戦だったMF部門。そんな名手たちの争いを制したのは、日本が誇るファンタジスタ・中村俊輔(1995・96年度出場)だ。横浜マリノスのジュニアユースから桐光学園に進学。8番を背負った2年次は初戦で東福岡に敗れたが、10番を背負った3年時は決勝で北嶋秀朗擁する市立船橋に敗れたものの、高校ナンバーワンMFの名に相応しいプレーを連発する。プロ入り後の活躍は、詳しく触れるまでもないだろう。42歳となった今なお、横浜FCでプレーしている。
2位には高校年代3冠を達成した“赤いすい星”の10番、本山雅志(東福岡/95・97年度出場)が入った。4-3-3のインサイドハーフを務め、パス良し、ドリブル良し、シュート良し、と三拍子そろったMFとして、古賀誠史、19位の宮原裕司(97・98年度出場)、金古聖司、手島和希らタレント軍団をけん引した。
その東福岡と“雪の国立”で決勝を戦った帝京のキャプテン、中田浩二(95・97年度出場)は9位にランクイン。正確な左足のキックと広い視野で優雅にゲームメイクをするボランチとして“カナリア軍団”を決勝に導くと、卒業後は鹿島アントラーズに加入。本山、19位の小笠原満男(大船渡/96・97年度出場)らとともに黄金期を築いた。
中田の大先輩にあたるのが11位に入った天才MF・礒貝洋光(85・87年度出場)だ。野性味あふれる風貌から繰り出される繊細なボールタッチとダイナミックなプレーは、間違いなく超高校級だった。
その礒貝擁する帝京と、12位の澤登正朗(86・87年度出場)擁する前年王者の東海大一による87年度大会の準々決勝は事実上の決勝戦と呼ばれ、スタンドに収まりきらない観客が大宮サッカー場のタッチライン際の特等席まであふれた。この試合は「高校サッカー史上に残る名勝負」とも言われている。
 2年から10番を背負った本田は3年時にはキャプテンに就任。自慢の左足で星稜を初の国立の舞台へと導いた【写真:YUTAKA/アフロスポーツ】
2年から10番を背負った本田は3年時にはキャプテンに就任。自慢の左足で星稜を初の国立の舞台へと導いた【写真:YUTAKA/アフロスポーツ】
このときの帝京には礒貝だけでなく、森山泰行、池田伸康、本田泰人、飯島寿久ら、のちのJリーガーが目白押しだったが、それ以上のタレント軍団だったのが、抜群のゲームメイクが光った6位の名波浩(88・90年度出場)が3年時の清水商業だ。同級生ではGK大石尚哉、DF大岩剛、薩川了洋、望月慎之、FW田光仁重、山田隆裕が、1学年下の望月重良、西ヶ谷隆之もプロになっているのだ。
異色なのは、13位の石塚啓次(92年度出場)だろう。石塚の選手権におけるプレー時間は、わずか22分。というのも、大会前の練習試合で右足小指に亀裂骨折を負っていたからだ。エースを欠く山城は「石塚を国立に連れて行く」を合言葉に勝ち進んでいく。国見との決勝は0−2と敗れたが、2点のビハインドの後半18分に“和製フリット”が登場すると、スタンドはどよめいた。
その山城を決勝で下した国見のエースが、14位の三浦淳宏(90・91・92年度出場)だ。プロ入り後に左サイドのスペシャリストとなる三浦は、高校時代はセカンドトップを務めるアタッカーだった。
長髪をなびかせながらスルーパスを繰り出した15位の上野良治(武南/89・90・91年度出場)は、礒貝に続く天才MFとして名を馳(は)せた。上野と同学年の鹿児島実業の前園真聖(89・90・91年度出場)は重心の低いドリブルを武器に2年時に準優勝に輝くと、3年時には3回戦で川口能活が守るゴールから2点を奪い、清水商業を退けた。
18年のロシア・ワールドカップに出場した日本代表選手では、3位の乾貴士(2005・06年度出場)、4位の柴崎岳(青森山田/08・09・10年度出場)、8位の本田圭佑(02・03・04年度出場)が20位以内にランクインした。
“セクシーフットボール”で旋風を巻き起こした野洲の一員だった乾は2年時に全国制覇を達成。連覇を狙った3年時の選手権は3回戦で敗れたものの、変幻自在のドリブルと繊細かつ大胆なボールコントロールは大会随一。横浜F・マリノスでは不遇をかこったが、セレッソ大阪で才能を大きく開花させた。
1年時から青森山田の10番を背負った柴崎は2年時に準優勝に輝いた。3年時は優勝する滝川二の前に3回戦で涙を飲んだが、「世代屈指のMF」に相応しく、絶妙なパスを連発した。卒業後は鹿島アントラーズを経て、17年1月からラ・リーガで奮闘中だ。
ガンバ大阪ジュニアユースから星稜に進学した本田は、1年時は初戦敗退、2年時は3回戦敗退を喫したが、キャプテンとして臨んだ3年時、その左足でチームをベスト4に導くと、名古屋グランパスでプロキャリアをスタートさせた。
(企画構成:YOJI-GEN)